九州大学・野島研究室博士課程3年の中山千尋と申します。新生RNA解析を用いて、RNAポリメラーゼIIの転写終結制御をテーマに研究しております。この度、RNAJ Travel Fellowship Programに採択いただき、ドイツ・ハイデルベルグで開催されたEMBL Symposium・The complex life of RNAに参加いたしました。この度はその参加報告をさせていただきます。
EMBL Symposiumの一つであるThe complex life of RNAは、EMBLハイデルベルグで2年に一度開催される学会です。EMBLハイデルベルグは、ハイデルベルグ旧市街から車で20分程度の山の中にある研究所で、周辺には牧場や森が広がる自然豊かな場所に位置しています。ハイデルベルグ旧市街にはハイデルベルグ城や哲学の道があり、歴史的な街並みを楽しむことができます。ハイデルベルグはアカデミックで国際的な都市としても知られており、街中でも英語が十分に通じます。学会会期中は、市内各地と研究所を往復するシャトルバスが出ており、市内のホテルに滞在して学会会場に向かう方が多かったです。シャトルバス内も参加者と交流する良い機会ですので、今後参加される方は是非利用されてください。
実は、今回の学会参加前に、英国に1週間滞在しました。レスター大学とキングスカレッジロンドンの共同研究者の元を訪れ、セミナーも開催してもらいました。単独での海外出張でしたので、とても緊張しましたが、大きな達成感を得ることができました。クリック研究所も見学させてもらったり、食事もご馳走になったり、ロンドンを大堪能した後、ロンドン郊外にあるヒースロー空港からフランクフルト空港に向かいました。フライト時間は1時間半と、福岡から東京よりも短いくらいです。電車だと複数の電車を乗り継いで7時間ほどかかるようです。フランクフルト空港からハイデルベルグまではDBと呼ばれるドイツの鉄道で1時間ほどかかります。ロンドンを堪能したツケなのか、今回はフライト・DB両方の大幅な遅延に見舞われ、ロンドンを出てからハイデルベルグに到着するまでに結局8時間ほどかかりました。一度EMBLのバイオインフォマティクスのコースに参加した経験があったため、ドイツの交通網には慣れたつもりでしたが、予想外のトラブルにかなり困惑しました。最安値のDBのチケットを購入すると、たとえ同じ区間であったとしても予約していない番号の電車に乗ることができず、自分の予約した番号の電車が来るのを辛抱強く待つしかありません。新幹線の自由席のような制度が存在しないことに不便さを感じました。DBの遅延・運休は日常茶飯事だそうですので、スケジュールがタイトな場合には、多少高くても融通の効くチケットを購入するといいと思います(研究室のボスに最安値のチケットの購入を強制されたわけではないことを強調しておきます)。
さて、学会が行われた会場は、EMBL Advanced Training Centre(ATC)と呼ばれる建物で、DNAの二重螺旋構造を模した建築が特徴的です。学会会期中は毎日ATCに通いましたが、足を踏み入れる度にその建築に感動していました。ポスターの設置箇所も、番号によってHelix A/Bと指定されます。

写真1. ATCの建築
初日は夕方からプログラムがスタートしました。会場に到着して参加手続きを済ませると、まずは夕食をとるスケジュールになっていました。夕食後の午後8時からクライオEMを用いた複合体構造解析で有名な英国MRC LMB のLori Passmore先生によるKeynote Lectureがありました。Poly A tailの長さの調節機構について、最新の知見を発表されていました。個人的に転写終結の研究をしていますので、大変勉強になりました。その後は各自ポスターを設置し、希望者は22:30まで残って自由にポスターを閲覧できるようになっていました。ポスター設置で印象的だったことは、写真撮影可否の意思表示、キャリア関連の意思表示(PhD/ポスドクポジションを探している・PIとしてポスドクを探しているなど)、コラボレーター募集中等のカードが事前に用意されており、ポスター発表者は自分の状況に合うカードをポスターと一緒に掲示することができる点です。私は日本の学会でこのようなカードを見たことがなかったため、合理的なシステムだと思いました。
2日目以降は、連日朝の9時から夜の8時過ぎまで学会プログラムが休みなく続き、体力的にとても大変でしたが、RNAにまつわる様々な研究を聞くことができ、学ぶことばかりでした。シンポジウムの名前の通り、RNAの転写から輸送・分解というRNAの一生を網羅する、幅広いRNA研究の演題がありました。研究に用いられているモデルも、ヒトや酵母だけでなく、植物や魚など多岐に渡っていました。私の研究はRNAシーケンス解析をベースに研究しているため、タンパク構造やRNA修飾の研究アプローチは新鮮に感じられました。また、ロングリードシーケンサーを用いたアイソフォーム解析・poly A tailの長さの研究も印象的でした。質疑応答時間には、大御所の先生だけではなく、学生が積極的に質問している姿に感銘を受けました。とても堂々としていて、かつクリティカルな質問をする方がいて、てっきりポスドクの方だろうと思っていたら、博士課程に進学して1ヶ月の学生と知って驚くと同時に、海外の学生のレベルの高さに圧倒されました。自分も一度だけ質問してみました。常套句かもしれませんが、Good Questionと発表者が言ってくれて嬉しかったです。また、国際学会なだけあって、さまざまなアクセントの英語が飛び交っていました。臆せず話してみることの重要性を学びました。
ポスターセッションは、初日の夜に目星をつけたポスターを中心に回りました。トップラボに所属する学生や研究者と直接話す機会は国内学会ではなかなかないため刺激的でした。そして、彼らもデータの再現性や解析に苦戦している話を共有してくれ、自分も地道に頑張っていくしかない、と勇気をもらいました。私のポスター発表は2日目にあり、Helix Aの上の方で行いました。エピジェネティック変化が転写終結に与える影響について発表をさせていただきました。トップレベルのRNA研究者や転写の専門家と濃いディスカッションができ、研究内容について沢山のフィードバックをいただきました。
発表の間のコーヒーブレイクの時間になると、参加者のほぼ全員がホールに出てきて、コーヒーを手に交流していることが印象的でした。私は今回一人で参加したため、まず話し相手を探すところからでした。同じラボから複数人で来ている人がほとんどでしたが、勇気を持って話しかければ、どのラボの人も会話の輪に入れてくれました。他には、面白い発表をしていた若手の研究者や、同様に一人で参加している方に話しかけてみることが多かったです。この学会では、全日程を通して昼食・夕食を参加者と共にするため、会話の輪に入る積極性と勇気が必要です。食事の席は自由でしたので、話したい人の隣に座れば自然と会話が弾みました。私が博士課程であると告げると、まずは今後のキャリアの予定(アカデミアかインダストリーか)を聞かれることに驚きました。アカデミアに興味があることを伝えると、いろんな方が欧州各国のアカデミックキャリア事情について教えてくださりました。余談ですが、ほとんどの人がLinkedIn・X・Blueskyのアカウントを持っていて、仲良くなるとそのアカウントを交換することが多かったです。国際学会に参加される際には、事前にこれらのアカウントを作って挑まれた方がいいかと思います。紙の名刺交換は一般的ではありませんでした。(何人かに紙の名刺をわたしてみたところ、珍しがって喜んでくれましたので、印象を残すという点では有効かもしれません。)
また、日本人参加者の方にもお会いすることができました。特に、大阪大学の廣瀬哲郎先生が招待講演者としていらっしゃっていました。製薬会社の方や海外でPIをされている日本人研究者の方もいらっしゃいました。2日目の夕食の際、英語でのソーシャライズに少し疲れてしまっていたところ、日本人の先生方の集まりに誘っていただきました。日本の学会でお見かけしても、ゆっくりお話することが難しい先生方から研究や留学生活について貴重なお話を伺うことができて感激しました。
学会最終日の夜には、お酒が振る舞われ、プロのバンドによる演奏を聴きながら、歌ったり踊ったりするパーティーが開催されました。さらに、パーティー会場に学会公式のフォトブースが設置され、思い出に写真を撮ることが可能でした。持ち帰った写真は大切にラボに飾っています。ハードなスケジュールの学会でしたが、最後まで皆さんバイタリティに溢れていて、自由に歌ったり踊ったりしている姿が印象的でした。日本人、というより東アジア人はシャイな方が多かった気がしますが、英国の研究室訪問で出会ったポスドクの方に誘われて、私も楽しく踊りました。このパーティーは深夜まで行われていましたが、私は翌日のフライトのことを考えて夜の10時過ぎには会場を後にしました。
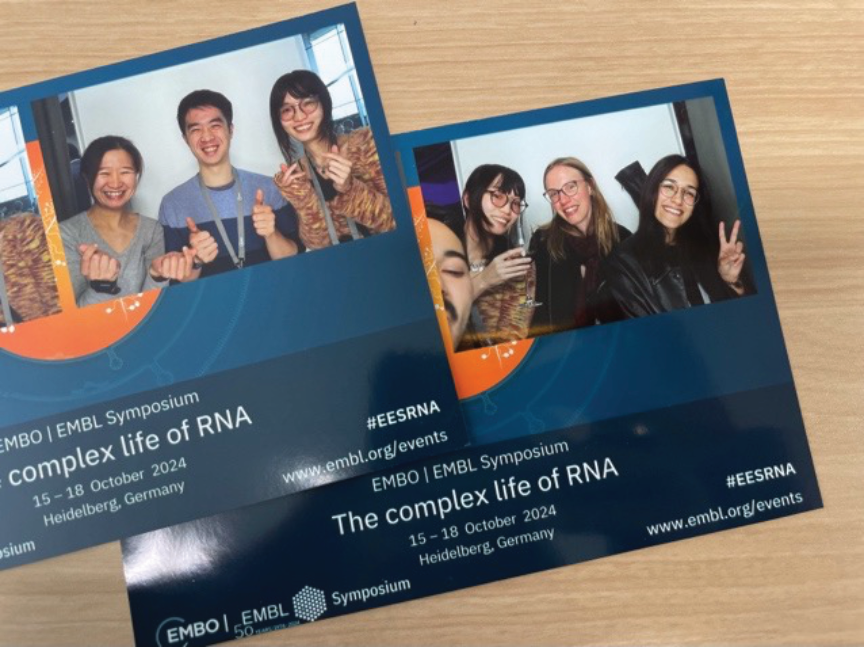
写真2. 学会に設置されていたフォトブースで取った写真
3日半の日程を通して、ほとんどの時間をATCで過ごし、研究や研究生活について意見を交換する、実りの多い学会参加となりました。博士課程の学生である私に、このような大変貴重な経験をさせてくださり、感謝しております。この経験を糧に、今後より一層研究に邁進していく所存です。最後になりますが、この度国際学会渡航支援を賜りました日本RNA学会の皆様に心より感謝御礼申し上げます。



