RNA学会の皆さま、こんにちは。徳島大学 先端酵素学研究所と東京大学 定量生命科学研究所でお世話になっております、小林穂高です。2023年10月から、若手PIとして研究分野を持たせていただき、RNAの細胞内1分子イメージングを武器に自分色のサイエンスをどんどん進めるぞと意気込んでいます。ラボにご興味ある方いましたら、いつでも気軽にご連絡ください(ラボウェブサイト:https://sites.google.com/view/h-kobayashi-lab)。
このたびRNA学会からご推薦いただき、文部科学大臣表彰 若手科学者賞をいただくことができました。microRNAは細胞内においていつ・どこで機能しているのか?といった、これまで見落とされてきた時空間的な側面に光をあてた点をご評価いただき、「RNAサイレンシングの細胞内時空間動態/制御の萌芽研究」という業績での受賞となりました。これもひとえに、3人の恩師である 福田光則先生・泊幸秀先生・Robert H. Singer先生をはじめ、困った時に手を差し伸べてくださる先生方、励まし合える同世代の仲間たち、至らない僕をサポートしてくれるラボメンバー、、、とにもかくにも沢山の人たちのおかげです。文部科学省との橋渡し役を務めてくださった、RNA学会の足達俊吾先生にも大変お世話になりました。才気あふれるスーパースターたちと比べ、僕はまさにモブのような研究者ですが、いかに多くの人たちに助けられてきたか、という一点においては負けない気がしています。これまで若手科学者賞を受賞されてきたRNA学会のお兄さんお姉さんたちに倣い、どういった紆余曲折を経て若手科学者賞の研究に至ったか、何か一つでも学生さん・ポスドクさんのヒントあるいは反面教師になればという思いで、とりとめなく書いていこうと思います。何の役にも立たないかもしれませんので、しょうもないネットニュース感覚で読んでいただければ。
20年も前の話ですが、栃木県の宇都宮高校に通っていた僕は、宇都宮高校が文部科学省のスーパーサイエンスハイスクール(SSH)に指定されたおかげで、地元の宇都宮大学で研究の真似事をする機会に恵まれました。GFPにSKL配列をつけることで、オルガネラの一つ、ペルオキシソームを可視化しようという実験です。真っ暗な部屋で接眼レンズを覗きこむと、まるで夜空にきらめく星のように細胞が光り輝いていました。研究者にとっては日常の一コマですが、生まれて初めて蛍光顕微鏡を覗きこんだあの瞬間の神秘的な感覚は、今でも覚えています。研究者になろうと思ったのは17歳のこの時です。SSHでお世話になっていた東京薬科大学の大島泰郎先生のご研究に憧れがあり、東京薬科大学を受験しましたが、合格して大学にお電話したところ、基礎をやるなら薬学部より理学部に行きなさいと言われ、そうなのかと東北大学の理学部に進学しました。
学部1,2年生のころは興味のある研究室に見学にいったり、図書館でThe Cellを読んだりするくらいで、ちゃんと研究をはじめたのは学部3年生の時です。正規の研究室配属まで待つこともないだろうと、理研の若手PI(独立主幹研究員)としてブイブイいわせていた福田光則先生が東北大学に異動されるタイミングで、福田先生のラボに入れていただきました。当時、若気の至りでたいそう生意気だった僕を根気よく育ててくださった福田先生には、今も頭が上がりません。福田研では、オルガネラ間の物質輸送(小胞輸送・メンブレントラフィック)を制御するRabタンパク質について、イメージングをメインに研究していました。研究ってこんなに楽しいんだ、そしてモブなりに人よりバット振るぞという気持ちで、9時から25時まで研究していました(が、ラボメンバーはほぼ同じ生活リズムだったので、人よりバットを振るには至りませんでした)。顕微鏡を覗いているとよく時間を忘れてしまい、睡眠不足がたたったのか、徹夜あけの学部4年生の誕生日に急性虫垂炎になって緊急手術→入院したりしましたが、退院日に病院から直接ラボに行き、そのままプログレスレポートをするくらい研究に首ったけでした。研究に熱中していたら、彼女から「私と細胞どっちが大事なの?」と愛想を尽かされ、研究に熱中していたら、運転免許が失効して通学用のバイクにも乗れなくなり、これは困ったと立派な十円ハゲができましたが、同じく研究に明け暮れていたラボの親友が「大丈夫だ、安心しろ」と言って極太マッキーで頭皮を塗りつぶしてくれたりして、楽しく日々を過ごしました。そんな折に、福田研の助教の先生が、後期エンドソームというオルガネラがRNAサイレンシングの活性制御に寄与しているという論文をジャーナルクラブで紹介してくれました。普段から、ノックダウン実験にsiRNAによるRNA干渉を多用していた僕にとって、それまで小さなRNAはあくまで「研究ツール」でしたが、小さなRNAは「研究対象」としても面白そうだという意識が芽生えました。その後、学部3年生の時に選んだ研究分野にこのままいるのもきっと楽しいけれど、それから一回り成長した博士号を取るタイミングで、研究者としてやっていく研究分野を選び直してみたいという気持ちが大きくなり、えいやとRNAの分野に飛び込むことにしました。

写真1:恩師1 福田光則先生(右)。Cold Spring Harbor Asiaにて。
一体どの研究室に行くべきか、そう思いながら色々と調べる中で、泊幸秀先生という若手のスーパースターが東京大学にいることを知りました。泊研の論文を読むにつれ、microRNAがどのようにして機能するのかという基礎の基礎を、磨き抜かれた生化学で、パズルのピースを一つ一つはめるように紐解いていくサイエンスに心打たれ、えいやとメールを送りました。何度も推敲して、福田先生にも見てもらい、誤字脱字がないかくまなく確認して、数日かけて長いメールを書きました。すると、泊さんからあっという間に短い返信があり、すぐにラボ見学の予定を組んでくださり、泊研から学振PDに申請させてもらえることになりました。ラボ見学の最後、泊さんから「今やっていることとずいぶん違うけど、本当にうちでいいんですか?」と聞かれ、慣れ親しんだ研究分野から、右も左も分からない研究分野に飛び込むことへの不安が、心の中で一気に膨らんだことを覚えています。それでも一瞬泳いだ目の先に、ふと泊さんのCellの論文が目に入り、この人のサイエンスを盗むんだと自らを奮い立たせ、よろしくお願いしますと答えました。勇気を出して、コンフォートゾーンから出ることを選んだあの時が、今に至るターニングポイントだったように思います。最初は上手くいかないことだらけで、丸2年間ほど全くポジティブデータが出ず、輝いているスター研究者たちと比べ自分には何が足りないのかと比較表をしたためるくらい悩んだりもしましたが(先述の彼女→今の奥さんが毎日おいしいご飯を作ってくれていたので、十円ハゲはできませんでした)、何とか3年目くらいから歯車が回り始めていきました。なかなか芽の出なかった僕を、それでもいつも温かく支えてくださった泊さんには、感謝しても感謝しきれません。泊さんがいかにいいボスかという小林さんの話はもう聞き飽きたとよく言われるので、今日はぐっと堪えます。今思うと、僕の場合、研究分野も(メントラ→RNA)、研究技術も(イメージング→生化学)、研究対象も(mammal→drosophila)、一度にがらりと変えてしまったので、自分のキャパの限界ギリギリだったように思います。50mlチューブにエタノールを55ml入れてフタ閉めるくらいギリギリでした。自分にとってどこまでが勇敢なチャレンジで、どこからが無謀な紐なしバンジーなのか、大きな決断の前には、学生さん・ポスドクさんにもよく自問自答・自問他答していただければと思います(才能MAXのスーパースターたちは、自分を基準にアドバイスすることがあるのでご留意ください)。

写真2:恩師2 泊幸秀先生(右)。研究室にて。
microRNAについて生化学を用いて研究していたころ、ずっと気になっていることがありました。microRNAはどのようにして機能するのか?というhowの部分にはみんな注目している一方で、細胞内においていつ・どこで機能しているのか?というwhen・whereは見過ごされているという点です。ですが、microRNA研究のメインストリームである生化学は、この問いに答えるのには向いていませんでした。生化学ではmicroRNAの活性などを「試験管内で」解析することが主だからです。ではどうすればmicroRNAの時空間的な側面に切り込めるだろうか。もともと細胞生物学の出身でイメージングが好きだった僕は、microRNAが機能する様子を「細胞内で」実際に見ることができればいいはずだ、これができればmicroRNAがいつ・どこで機能するのか自ずと分かるはずだと考えました。ですが、タンパク質とは異なり、RNAのイメージングは一般的ではありません。そんな折に、泊研の助教の先生が、RNAの1分子イメージング技術を確立した米国のliving legend、Robert H. Singer先生の論文をジャーナルクラブで紹介してくれました。直感的に、Singerラボ(Albert Einstein College of Medicine / HHMI Janelia Research Campus)に留学すればできそうだなと思いました。当時、泊研の助教にしていただいたばかりのタイミングでしたが、泊さんは僕の第二のチャレンジを全面的に応援してくださり、そこで、microRNAの機能を可視化するプロジェクトをやりたいですとRobにメールを打ちました。今になって思えば、あれだけの大御所の先生に何のつてもなくメールするのはなかなか無謀で、最初はメールの返信がありませんでした。が、それでもRobのラボに留学したかった僕は、メールの文面やタイミングを変えながらアプローチを続けたところ、6通目のメールの後にRobが「推薦書を送ってくれるかい?フェローシップはとれるかい?」と反応してくれました。当時のボスである泊さんに加え、福田先生とNicholas Ingolia先生(UC Berkeley)がすぐ推薦書を書いてくださり、さらに大好きな泊研OBの方が、Janeliaで直接Robに僕を売り込んでくださり、はれて海外学振で留学することができました。3年間の留学中、いつも「Hotaka, うまくいっているかい?」という言葉を呼び水に、研究だけでなく、現地での生活や家族の心配事など、何から何までサポートしてくれたRobには、感謝の思いでいっぱいです。留学を終え日本に帰るとき、新型コロナのパンデミック中だったにも関わらず、いいから送別会やるぞと言ってくれたり(もちろん感染対策を徹底した上で)、Robは僕だけでなくラボメンバー全員から愛される最高のボスでした。Robのおかげで、microRNAが細胞内で機能する様子を世界で初めて可視化することに成功し、その時空間解析を行うことができました(Kobayashi & Singer, 2022, Nature Commun.)。そしてこれが、若手科学者賞のメイン論文になりました。
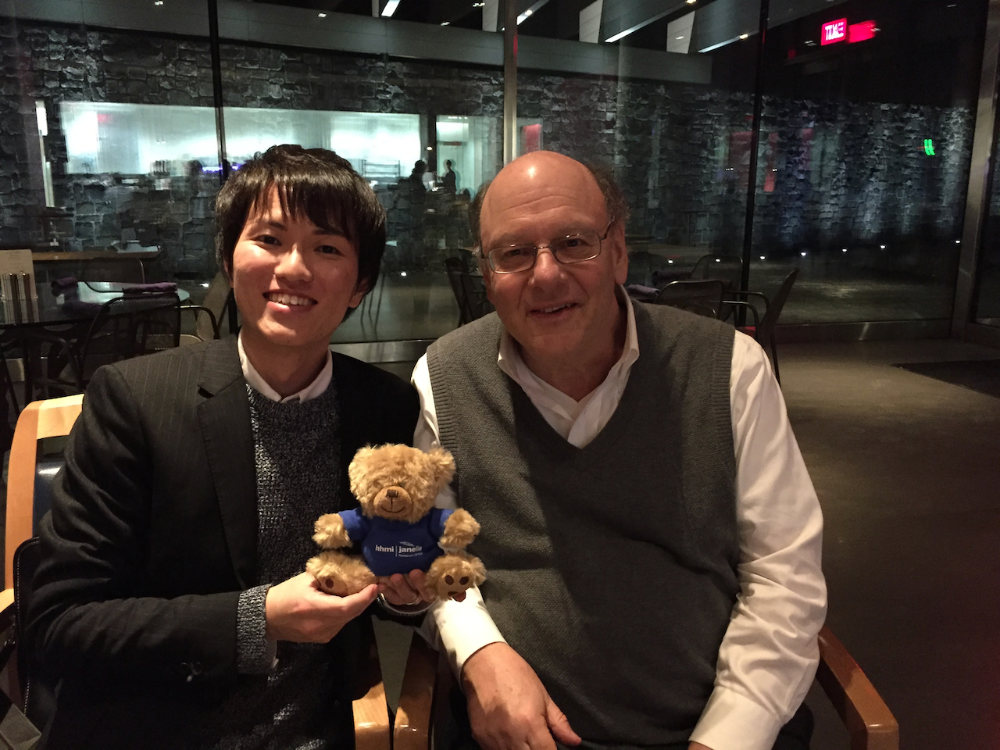
写真3:恩師3 Robert H. Singer先生(右)。HHMI Janelia Research Campusにて。
4000文字程度で、とのお話でしたのでこの辺りで、、、。本当は3人の恩師だけでなく、これまでのキャリアの大事な局面(ラボ選び・グラント・ジョブハント・研究場所などなど)でここぞとご支援くださった先生方についても、エピソードと共にお名前を出したかったのですが、今回は我慢しまして次の機会に。徒然なるままに書いてしまいましたが、研究者を志してからの20年を振り返ると、やはりいつも誰かに助けられてきました。純粋に運がいいという部分もあると思いますし、もしかすると毎日の基本的な挨拶や、相手をリスペクトしていることが伝わる言動、モブはモブなりにもがいている姿などが、まあ助けてやるかという気持ちを引き寄せた部分もあったかもしれません(何度かそう言われました)。これからは、助けてもらうだけでなく、大切なラボメンバーをはじめ、より若い人たちの大事な局面を助けてあげられるよいPIにならねば。この文章を書く機会をいただいたおかげで、改めてそう感じました。頑張りますので、RNA学会の皆さま、今後ともご指導のほどどうぞよろしくお願いいたします。




